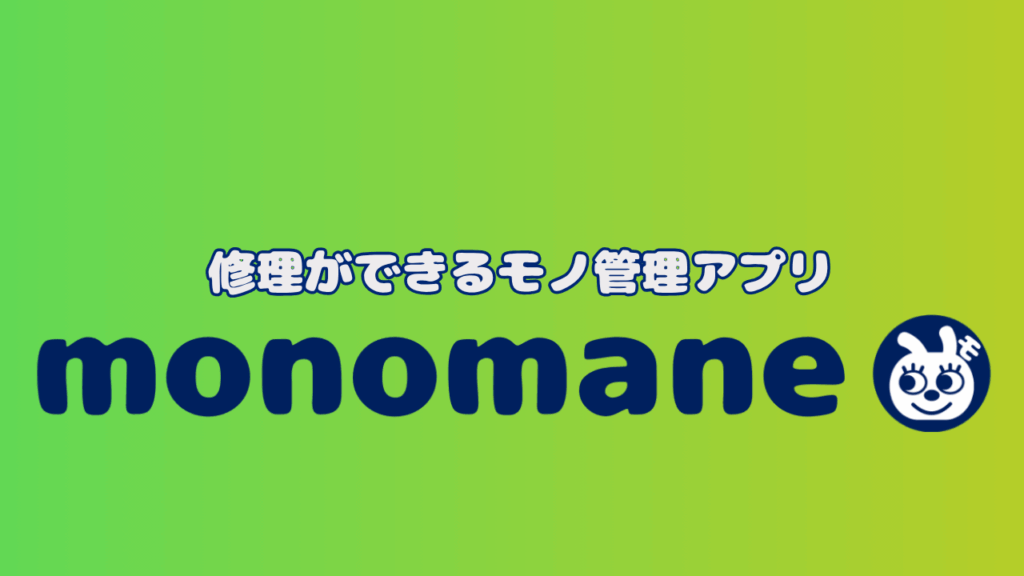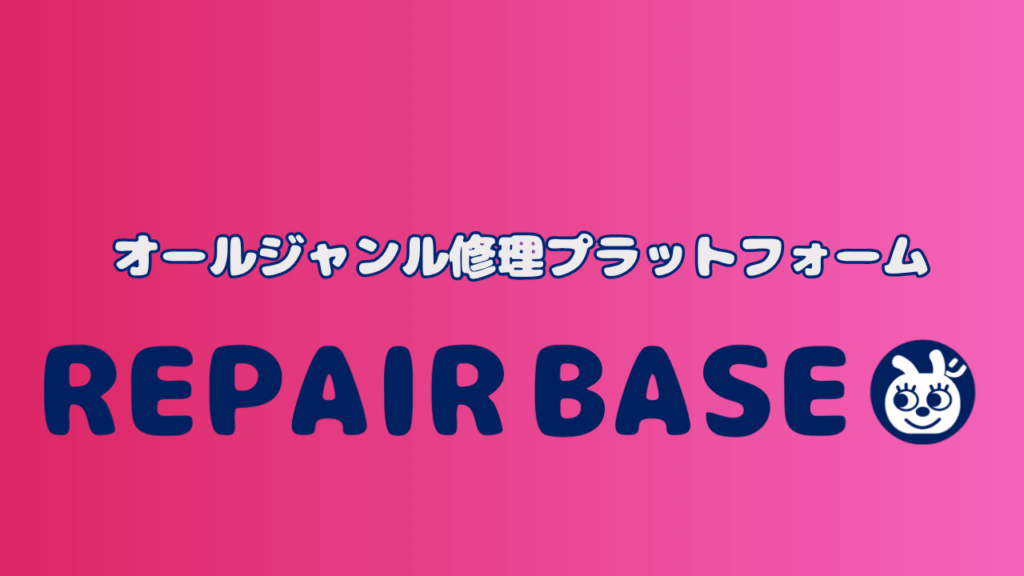はじめに
皆さんは修理する権利(Right to Repair)をご存じですか?
欧米で整備が進む権利で、地球環境を守るための大切な考え方です。このページでは、「修理する権利」に関する世界の動きや日本の現状をわかりやすくご紹介します。
-目次-
1. 修理する権利とは?
「修理する権利」とは、自分の持ち物を自分で直す、または修理をお願いする人を選ぶ自由であり、そのための情報が十分に提供される権利です。
かんたんに言うと、自分が買ったものを自由に快適に直せる権利のことなのです。
皆さんはこんな経験ありませんか?
- 洗濯機が壊れちゃったけど、ネットで調べてもどこに依頼していいか分からない。メーカーに依頼したら高額な見積が出てきた。(選択肢の制限)
- メーカーから部品が手に入らないから直せないと断られて、買い替えるようにすすめられた。(部品供給の制限)
- 修理の見積を出してもらったけど、比較もできないから高いのか安いのかすら分からない。(修理情報の不足)
これは修理する権利が正しく確保されていない状態です。でもそれが日本では当たり前かもしれません。モノが壊れた時はただでさえ困っているのに、こんな状態では修理する気も起きなくなりますよね。
2. 欧米ではどうなっているの?
実は、欧米ではここ数年で「修理する権利」の整備が急速に進んでいます。
<欧米における修理する権利>
| エリア | 方針 | 最新動向 |
| アメリカ(州単位) | 所有者が自分で修理できる状態を作る | デバイスを中心に、メーカーに対して修理マニュアルと部品の供給を義務化。農業機械も所有者が自分で修理できるように。 |
| ヨーロッパ(EU) | 所有者が信頼できる人へ修理を依頼できる、選択できる状態を作る | 修理しやすい設計を法制化し、「修理しやすさ」スコアを表示。 加盟国に対して、修理業者を選べる修理プラットフォームの整備を義務化。 |
アメリカとヨーロッパでは方針が少し異なるものの、どちらも修理してモノを大切に長く使用するために法整備が進み、「修理する権利」が当たり前になってきています。これは「修理する権利」の拡大が、地球環境やサーキュラーエコノミー(循環型経済)に良い影響を与えるということを示しています。
3. 日本ではどうなっているの?
日本では「修理する権利」の認知度も低く、法整備も進んでいません。所有者が自分でモノを修理する自由も、信頼する修理者へ依頼する自由もほとんど確保されていないのが実情です。そのため、次のような事象が当たり前になってしまっています。
消費者
- メーカー以外の修理依頼先がない。
- 修理の選択肢が少なく、金額の比較ができない。妥当性が分からない。
- メーカー修理以外は保証がなくなる。動作に制限が発生する。
修理業者
- 修理方法が公開されていないため、修理ができない。
- パーツが適切に供給されない。(確保されていない)
- 提携メーカー以外扱えず、積極的に修理を提供することができない。
4. 修理する権利がないと、どうなるの?
修理する権利が浸透していない状況では、「直して使う」という選択肢の優先度が下がります。必然的に買い替えが促進され、本来であれば、まだ直して使うことができるモノが廃棄されてしまうことになります。
- 過剰な廃棄、過剰な生産が増え、地球環境に悪影響を与える
- 修理よりも高い「買い替え」を迫られ、不必要な費用が掛かる
- 実際に修理を担う修理業者の収入が減り、廃業や人材不足になる
- 地方では修理を提供できる企業や技術者が不足する
- メーカーも修理する技術者を確保できなくなる
上記のように、地球環境はもちろん、社会経済的にも悪循環に陥っているのが今の日本の現状です。危機的な状況を多くの人に知っていただく必要があります。
5. わたしたちにできること
この悪循環を少しでも改善するために、わたしたちにできるのは次のような行動です。
- 修理ができる製品を選ぶ
- 修理ができるお店を調べておく
- 長期的な修理提供に前向きなメーカーを応援する
- 直して使うことの大切さや「修理する権利」の存在を周囲に伝える
とはいえ、「修理する権利」が正しく確保されるためには、安全性を考慮した法整備やメーカー各社の理解・協力が必要です。
6. まとめ
「修理する権利」は、私たちが本来持つべき権利です。そして、モノを直して大切に使うことは、地球環境・家計・経済にやさしい、とても素敵な選択です。もし何かが壊れてしまったときには、買い替えではなく「直して使う」ことをぜひ検討してみてください。モノを買うときは、修理してもらえる製品かどうかも確認してみるといいかもしれません。
R&Rは、「修理する権利」の推進や情報の発信を積極的に行っています。そして、修理の利便性や収益性を高めるために、モノの管理と修理をストレスなくスムーズに行えるアプリケーションや修理業者の方向けのオールジャンル対応修理プラットフォームを現在開発しています。(2026年1月)
モノを直して大切に使うって素敵。修理できるってかっこいい。
R&Rはそんな考え方を浸透させ、修理業界を変えたいと考えています。私たちの考え方に賛同いただける方や一緒に「修理する権利」を推進いただける方はぜひ「CONTACT」よりご連絡ください。